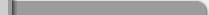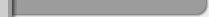鈍行モデラーのNゲージ工作&収集・ブログ風味。その他モロモロ添え。
|
この工作記事の続きを書くの、どれだけぶりでしょう? ・・・ちらっと調べてみたら、1年と数ヶ月ぶりでした(汗) まだ完成してないことがお恥ずかしい限りで・・・ 郵袋室の扉を、如何にして他の扉と同様な仕様にするか・・・で暗礁に乗り上げていたのですね。 結局二転三転して、上の写真の上方に写っているイエロートレインさんのパーツを使うことにしました。 ただし、そのままでは使えませんので、多少の加工が必要となります。 今日はそこまで作業が進んでいないので、その説明はまた後日に・・・ 今日はとりあえず、側板の郵袋室扉を開口する作業だけ行いました。 写真で見るとあっと言う間ですね(^^; 実際は結構な時間を費やしているんですが・・・ この裏側はパーツをはめ込む都合上、パーツ貼り付け面をツライチにする作業で苦労しました。 写真も撮っていたのですが、かなり見た目が汚いので割愛いたします(笑) 久しぶりの工作再開記事はたったコレだけ(汗) でも、今日の工作は晩ご飯の後に始めて、夜中の1時過ぎまでかかった作業なんですヨ。 相変わらずのカメですよねー(笑) さて、次回は扉パーツの加工となります。 取り付けまで進められればいいのですが・・・ <追記> 過去記事が相当むかしまでさかのぼる必要があるので、リンクを設けておきます↓ オユ10 2557の製作・その1 オユ10 2557の製作・その2 オユ10 2557の製作・その3 オユ10 2557の製作・その4 オユ10 2557の製作・その5 オユ10 2557の製作・その6 オユ10 2557の製作・その7 オユ10 2557の製作・その8 下はさらにそれ以前の記事(マニ36の製作と同時進行していた頃の記事です。オユ10の製作記事が含まれるもののみを抜粋しました。これらの記事の後に「仕切り直し」として上記の記事にチェンジしています。)↓ 荷物車の製作・その2 荷物車の製作・その6 荷物車の製作・その7 荷物車の製作・その8 PR |
 |
|
先日入線紹介をしたフライシュマンのBR182ですが、DCCサウンド機能を含めたテスト走行の模様を動画にしましたのでご覧ください。 レイアウトがあるわけではないので、見た目がみすぼらしいですが・・・(笑) レールはフライシュマンのデジタルスターターセットに同梱されていたものを使用。 コントロールも同じセットのmultiMAUSという制御器を使用しています。 ファンクションは以下の通りです。 F0:ヘッドライト/テールライト(multiMAUSではライトボタンで制御) F1:サウンド・オン F2:警笛ミックス(高+低) F3:警笛(低音) F4:ハイビーム(ヘッドライト) F5:発進時ホイッスル F6:加減速慣性・オフ(フライホイールを搭載しているような動きをオフにする) F7:コンプレッサー音 F8:アナウンス(ドイツ語) F9:Shunting gear(何て訳すのか判りませんが、使用すると低速モードになります) F10:ミュート(消音) F11:警笛(高音) F12:客室アナウンス(ドイツ語) F13:客室アナウンス(ドイツ語) F14:駅構内アナウンス(ドイツ語) F15:駅構内アナウンス(ドイツ語) F16:連結音 F17:客室アナウンス(ドイツ語) F18:客室アナウンス(ドイツ語) F19:加速指標(よく判りませんが、「Meep meep」と言う音声が流れます) ※動画ではF6・F8~F10・F12~F19は使用してません。 |
 |
 |
|
忍者ブログ [PR] |