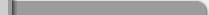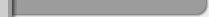鈍行モデラーのNゲージ工作&収集・ブログ風味。その他モロモロ添え。
 |
|
タイトルはこんな感じにしてますが、実はそれがメインではなくて、運転免許の更新に鴻巣へ行ってきたわけで・・・ 5年前の更新時には突然この機関車を発見して、ケータイで撮影した写真をこのブログでもご紹介したのですが、今回は初めから思いっ切り写真撮影をするつもりでデジイチをカバンに入れて訪問しました。 (5年前の記事はコチラ→静態保存機発見) ところがまあ、お昼ごろから降り始めた雨はかなりの大粒で、時々結構な大きさの雪まで混じる始末。 寒いし、カメラは濡れるし・・・ でも、せっかくカメラ持参で免許の更新に来たんだし、メゲてもいられないので数枚だけですがきちんと写真を撮って参りました(免許の更新そっちのけですね・笑)。 ここ鴻巣の「せせらぎ公園」に保存されているC11は322号機です。 特徴的な角型ドームから4次形であることが分かります。 C11は3次形からタンクが若干大きくなり、サイドタンクの下のラインがキャブ下のラインとツライチであったそれまでの形とは異なって、少々武骨な印象があります。 タンクの上のラインもほんの少し高くなり、側面のキャブ窓の中ほどの高さまでせり上がっています。 その3次形を戦時設計に変更したものが4次形になります。 具体的には、戦時下で貴重であった鉄などを節約し、かつ製造工程を簡略化したグループで、木製のデフ板や、比較的簡単に製造できる角型のドームを装備していました。 戦後は普通の3次形と同様のものに戻されたものがほとんどだと聞いていますが、ドームについてはそのままの車両が多かったのではないのでしょうか? 塗装もきちんとされていて、とても手入れが行き届いていますね。 なかなか素晴しい保存状態でした。 あ、そういえば新橋駅前のC11も角型ドームの4次形でしたね。 新しい形の方が程度も良くて、保存し易かったのかもしれませんね。 |
 |
|
忍者ブログ [PR] |